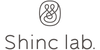前回に引き続き、マルニ木工の広島工場を訪れ
研修を通して学んだこと感じたことをブログ形式でお伝えして行きます😊
第2弾の今回は、マルニ木工を代表する
「HIROSHIMA」アームチェアの歩みと製造方法について
ご紹介していきます!
日本から世界の定番を
マルニ木工の名が世界的に広まるきっかけとなったのが
2008年の「HIROSHIMA」のアームチェアの発売です。
2023年の広島サミット(G7)の会場や
Apple本社のカフェスペースに採用されたことでも有名です。
「この椅子はなんだ!?」と世界各国の要人を魅了した
その驚くべき座り心地と美しいフォルムを実現できたのは、
マルニ木工の卓越した技術と、
デザイナー深澤直人さんとの出会いからスタートしています。

HIROSHIMAアームチェアの歩み
2005年 「nextmaruni 」で深澤さんと出会う
国際的な外部デザイナー12人との協働プロジェクト「nextmaruni」。
12人のデザイナーの中に、深澤さんの姿がありました。
「日本の思想や美意識から生まれた椅子」 をゴールとし、
各人の視点でチェアをデザイン、製作していきます。
その中で、深澤直人さんは
「デザインしたものをどれだけ形にできるか」を確認するために
マルニ木工の工場に足を運びました。
「マルニ木工にはデザインを形にする職人技と量産技術の両方がある」
そう感じた深澤さんは、
マルニ木工の工場を訪れ、nextmaruni のアームレスチェアを作り上げました。
2008年 MARUNI COLLECTION発売
2007年に入ると、12人の中で
最もマルニ木工の強みを理解していた深澤さんとタッグを組み
MARUNI COLLECTIONの発表へモノづくりがスタートします。
「ずっと良い木の椅子をデザインしたいと思っていた」
という深澤さんの想いとマルニの工業化技術が合わさり、
マルニ木工を代表する名作「HIROSHIMA」が誕生しました。
HIROSHIMAを大量生産するには、専用の加工機械が必要でした。
それもただの機械ではなく、
職人が手作業で仕上げるのと同じ精度と動きを実現することが求められます。

そこで活躍するのが、マルニ木工の「プログラミング職人」です。
プログラミングを駆使して、加工機械をカスタマイズし、
木の削り方の順番やスピード、角度まで細かく調整しながら、
品質の安定・作業効率・コストのバランスを考えて調整を重ねていきます。
試行錯誤を重ね、職人技を機械に宿らせることで、
HIROSHIMAの美しいフォルムと心地よさが生まれました。
HIROSHIMAの名付け親

「HIROSHIMA」という名前は、深澤さんが名付けられました。
---------------------------------------------
HIROSHIMAという名前は平和の象徴として
世界の多くの人が知っていて、一度聞くと忘れない。
これからは地方の中小企業がダイレクトに世界へ発信し、
積極的に繋がっていく時代になる。
マルニがこれから本格的に世界展開をしていく上で、
とても相応しいネーミングだと思う。
---------------------------------------------
そう深澤さんは話してくれたそうです。
"広島から世界へ挑戦する"という思いが伝わりますね。
HIROSHIMAが出来上がるまで
ここからはHIROSHIMAが
どのように作られていくかを工程に分けてご紹介していきます。
1. 木材の品質を確認する

HIROSHIMAに限らず、
マルニ木工が製造する家具は、高品質な木材のみを使用しています。
家具に使用できる板材は、成長した木の約4割から
さらに切り出した残り2割のみ!
厳選した木材のみを使用して、HIROSHIMAは作られています。
加えて木材を仕入れた後に、2年をかけて乾燥!
写真に映る大きい乾燥施設で、木一つ一つの含水量(木材が含む水分量)を8%〜10%まで減らします。
2. 板のサイズを揃える
続いて、多種類の家具を製造するにあたって
板のサイズを揃える必要があります。
木材それぞれの木目や欠点を見極めながら
指定のサイズに切り揃えて行きます。
3. 部品の形に切り出す
 職人の手によって木を形取ったり、
職人の手によって木を形取ったり、
パーツによっては機械が切り出していきます。
マルニ木工では、木目が見える塗装も多いため、
木目や木の質感などが製品の品質に大きく影響します。
そのため同じ種類の木であれば何でも良いという訳ではなく、
可能な限り左右の肘や背もたれの
木目や色味が揃うように選別しながら切り出していきます。
4. 木を曲げる
切り出した板を加熱しながら、プレス機で圧縮成形していきます。
HIROSHIMAの座面が曲線を帯びているのも、この工程を経ているから。
HIROSHIMAの座面をよく見てみると
6枚の曲げ板を合わせて一枚の座面に仕上げているのがわかります。
5. 部品を加工・組み立てる
 ゆったりともたれる背中と肘掛けは、
ゆったりともたれる背中と肘掛けは、
体をしっかり支える椅子の中でもとても重要な部分ですが
マルニ木工では、フィンガージョイントという凹凸をつけた接着手法で
接着面積を増やし強度を上げる工夫が施されています。
6.工作ロボットによる削り加工
 マルニ木工には熟練の技を持つ職人もいますが、
マルニ木工には熟練の技を持つ職人もいますが、
HIROSHIMAアームチェアは機械が12本の刃物を使い分けながら削り出しています。
機械で、X・Y・Zの3軸に加え、傾き・回転の複雑な動きを実現するために
高度なプログラミングが必要になりますが、
マルニ木工には、機械をまるで職人の手のように自由自在に操る
職人技を数値化する「プログラミングの職人」がいるため、機械を使った量産が可能なのです!
7. 組み立てと磨き

HIROSHIMAの特徴的な曲線美は、
1脚1脚職人が全て手作業で磨いていることをご存知ですか?
小さな凹凸や微妙な角度を調節しながら
なめらかな触り心地を実現するのは、
機械にはできない、職人の眼と手が必要不可欠です。
マルニ木工でこの磨きを任されるのは、3人だけなんだとか!
技術はもとより、1日中立って磨き続ける体力も求められる精鋭チームがマルニ木工の要を担っています。
8. 塗装する

椅子を吊り下げながら裏までもまんべんなく塗っていきます。
9. 最後の検査と梱包

この写真に写っているHIROSHIMAは全て、検査に不合格とされた部分です。
厳正な基準を通過したチェアのみが、皆さんのもとへ届けられます。
いかがでしたか?

マルニ木工では、高度な機械加工によって
複雑なデザインを安定した品質で仕上げる一方、
木目の美しさや手触り、絶妙な角度の調整は職人が担ってきました。
最後の仕上げでは、職人が1脚ずつ丁寧に磨き上げ、
思わず触れたくなるような滑らかな手ざわりに仕上げています。
そうして出来上がるHIROSHIMAは、
マルニ木工の「機械と職人の技術力の結晶」とも言えると思います。
世界各国の要人を魅了したのもうなづけますね☺️
次の記事では、「マルニ木工で活躍する職人」を深掘りします!
Shinc lab.スタッフが広島県のマルニ木工の工場を訪問しました。普段はなかなか見られない工場の様子を、ぜひ記事でご覧ください。