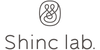今回の記事で第3弾になる
「マルニ木工工場見学レポート」ですが、
だんだんと皆さんもマルニ・マニアに
近づいてきたのではないでしょうか?(笑)
知れば知るほど奥深いマルニ木工さんですが、
今回は「HIROSHIMA」の製造を支える「職人」に
スポットを当ててご紹介をさせていただきます!
どんな職人が働いているの?
「ものづくり」の観点で見ていくと
10名もの職人さんが関わっています!
①板材の購買・管理
まず大切な材料となる木材。
工場見学をしていて気づいたのは、
見渡す限り「節のある板材が無い」ということ!

外の倉庫にも、工場の中にも多くの板材が置かれていましたが
みんな綺麗な木目の板しかなく
マルニ木工さんの妥協のない木材選びのこだわりが感じられました。

②木取加工と③組み合わせ
HIROSHIMAアームチェアの背もたれは
実は木目の美しさを見極めながら
4枚の板を組み合わせ丁寧に加工されています。

さらに、肘の部分にも注目してください。
まっすぐ美しく伸びた木目は「柾目(まさめ)」と呼ばれる
希少な部分を使用しており
左右で同じ木目になるように職人が厳選しています。

実は肘の木目まで揃えて仕上げるメーカーは、そう多くありません。
全ての木目が美し過ぎて見落としがちな点ですが
マルニ木工はそこまでこだわります。
④機械加工
実は、機械加工に至るまでの過程には
職人の手作業が欠かせません。
まず、職人が試作品を手作業で製作し
その後「機械化しても安全に、誰でも正確に製造できるか」
を考えながら改良を重ねていきます。

さらに、完成した試作品をもとに
機械での製造を可能にするためのプログラムを組む専門の職人がいて
初めて生産が実現するのです。

精巧なものづくりの裏側には
職人たちの技と知恵が詰まっています!
⑤仕上げ・組み立て
HIROSHIMA椅子の背もたれと肘は
体をしっかりと支える重要なパーツ。
そのため、職人の精密な技術と丁寧な作業が欠かせません。

この工程は、単に接着するだけではなく
職人が木のわずかな歪みを見極めながら
最適な力加減で締め上げることで
なめらかで一体感のある仕上がりになっています。

こちらは、肘と脚部分を接続している様子です。
強さと美しさを両立させる精巧な技が
HIROSHIMAアームチェアの心地よさを支えています✨
⑥磨き
現代ではロボットによる磨き作業も可能になっていますが
HIROSHIMAアームチェアのように
全体に滑らかな曲線が施されたデザインでは
やはり人の手作業が不可欠です。

快適な椅子には座り心地だけでなく、
触り心地も重要な要素と考え
職人は細部まで丁寧に磨きをかけ
滑らかな質感に仕上げます。
思わず触れたくなるあの滑らかさは
職人の手作業によって生まれるものなんですね!

長時間にわたる集中力と体力を要する職人の姿は
まさにアスリートでした!
⑦塗装
磨き加工を経て
節や割れの基準をクリアしたHIROSHIMAアームチェアは
職人の熟練した技によって均一に塗装が施されます。

塗装は単に色や質感を加えるだけでなく
木の導管を埋めることで
木材の変色やゆがみを最小限に抑える重要な役割も果たしています。

⑧裁断
座面や背もたれに使用されるファブリックやレザーは
まず職人の手によって慎重に裁断されます。

その際、木製のフレームにぴったりと合わせるため
素材の特性を見極め
最適なサイズで正確に裁断することが求められます。
ファブリックの柄は、裁断・裁縫の職人の技術によって
繋ぎ目をぴったりと合わせることで美しい仕上がりを実現します。
⑨縫製
裁断後、縫製が行われます。
ここでは、素材の美しさを引き立てつつ
耐久性を確保するために、
精緻で丈夫な縫い目を施す技術が重要です。

職人は、細部にまで気を配りながら
座り心地を左右する部分を一針一針丁寧に仕上げていきます。
⑩張り
工場では、ラウンディッシュソファの
「張り」作業を見学させていただきました。

職人がシワやタルみが出ないよう
慎重に力を入れてファブリックを引っ張る様子は
長年培われた技術の賜物でした!
実はHIROSHIMAの張座は
取り外し可能なカバーリング仕様になっています。

家庭でも簡単に座面カバーを交換でき
長期間清潔に保つことができるため
実用的な点も人気の理由となっています😊
いかがでしたか?
1脚の椅子が完成するまでには
実に多くの職人たちが関わっており
その過程を知ることで
ものづくりに対する妥協のないこだわりが伝わってきます!
材料選びから製造に至るまで
一つひとつに職人たちの技術と情熱が注がれていました。
マルニの椅子は、まさに一生のパートナーとなる家具だと思います。
自分のパートナーとなる椅子が
こんなにも愛情を持って製造されていることを知ると
なんだか嬉しくなりますね♪
日々触れるものだからこそ
見た目や価格だけでなく、
座り心地や職人の技術にも目を向けていただけると、
より一層その魅力を感じていただけると思います🌟
次の記事では、
マルニ木工の「木材へのこだわり」について
ご紹介いたします!
Shinc lab.スタッフが広島県のマルニ木工の工場を訪問しました。普段はなかなか見られない工場の様子を、ぜひ記事でご覧ください。