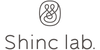Shinc lab.のスタッフは毎年、マルニ木工の広島工場を訪れ
ものづくりの現場を実際に見て学ぶ機会をいただいています😊
このブログでは
研修で学んだことや感じたことを
皆様にもお伝えしていければと思います。
第1弾は、「マルニ木工を知る」。
まずは、マルニ木工の歴史や会社の思いについて
ご紹介していきます!

日本を代表する木工会社「マルニ木工」
皆さん、「マルニ木工」という会社は知っていますか?
日本で3番目に古い歴史を持つ
創業97年の老舗家具メーカーです。
代表作としては2008年に発売された
「HIROSHIMA」アームチェア。
2023年の広島サミット(G7)の会場や
Apple本社のカフェスペースでも採用されました。

マルニ木工の歴史をたどる
1928年 マルニ木工の誕生
「工芸の工業化」を掲げ、近代的な産業として木工業を興したい、
日本の住宅文化のレベルを高めたいという強い思いと理念を持って
マルニ木工は創業しました。
そんな思いを込めて、1928年にマルニ木工が誕生しました。

創業者の山中武夫さんは
もともと呉服店を家族で営んでいましたが、
広島・宮島の木製の伝統工芸品に魅了され
当時では難しいとされていた
「曲げ木(まげき)」の技術を確立していきます。
そして、この技術を活かして生まれたのが
マルニ木工の最初の椅子「曲木椅子(銀行椅子)第1号」。
戦前に大量生産され、多くの人に愛用された一脚です。

1940年代 太平洋戦争〜第二次世界大戦
戦争中は、家具づくりどころではなくなり、
軍事品の生産へシフト。
戦闘機の部品を作ることもあり精度を求められ
さらに鉄不足の影響で、
なんでも木材で作らなければならず
この時期に木工技術がさらに磨かれることに…!

1946年 欧米化の波に乗る
戦後、日本がいち早く復興するきっかけとなったのが
進駐軍からの大量の家具注文でした。
その中でも象徴的なのが
進駐軍宿舎用の「カードチェア」。
実は当時、日本には「椅子」という文化がほとんどなかったため
進駐軍の人々はとても驚いたそうです!
(確かに、当時の日本では「ちゃぶ台に座布団」が当たり前でしたよね!)
さらに、マルニ木工は木材の人工乾燥技術の研究・開発をスタート。
高度な木工加工を実現するために
新たな技術を次々と導入していきました。

こうした挑戦が実を結び
やがて「技術のマルニ」と称される礎が築かれていきます。
1950年代 日本の生活スタイルに変化
1955年、マルニが製造・販売した
デッキチェア 「オアシス」 が大ヒット!
当時の猛暑も追い風となり、爆発的な人気を記録しました。
さらに、洋家具づくりで培った曲げ木の技術を活かし、
肘掛けや足台の快適さを追求したことで、
「ベランダにはマルニのデッキチェア」が定番に。

戦後わずか10年で、
こんなにも革新的な生活スタイルが実現したことに
技術革新と洋風化のスピードに驚かされますね!
1960年 応接セット「No.79みやじま」誕生
海外輸送の効率を考慮し
分解・組み立てが可能なノックダウン式を採用して設計されました。
輸出用フレームは国内でも好評を博し
「みやじま」として日本でも親しまれるようになりました。
そして、2006年に「マルニ60」として復刻され
今もなお、多くの方に愛されています。

「みやじま」という名前は
広島県宮島の世界文化遺産厳島神社にちなんでいます。
アーム部分を横から見ると
まるで鳥居のように見えるんですよ⛩️
実は、厳島神社では約60年前のみやじまが
今も見ることができるんです!
私たちスタッフも大興奮で
たくさん座って写真を撮ってきました✨

復刻されたマルニ60は
当時のサイズやノックダウン式の構造をほぼそのまま再現しています。
その丈夫さと、時代に流されない独自の魅力が
時を超えて愛され続けている理由だと実感しました🌟
1960年〜1970年代 「工芸の工業化」
生産技術の進展により
初めて彫刻を取り入れた製品が登場しました。
まずは職人が手作業で彫刻を施し
そのデザインを機械化することで
消費者が求める市場価格で供給できるようになりました。

ただ機械に任せて大量生産しているわけではありません。
彫刻技術やデザイン性を持ち合わせた職人と
さらにその技術を機械化する職人がいるからこそ
成し遂げられたことだと思います!
すごい技術力ですよね!
1990年代 バブル崩壊 倒産の危機
90年代、バブル崩壊とともに
中国製の安価な家具が市場に流通し
マルニ木工の経営は大きく傾いていきました。
倒産の危機が迫るなか
改めて木製家具という原点に立ち返り、新たな挑戦を決意。
技術力はピカイチ。
だからこそ時代のニーズに合わせた
次の家具づくりが求められていたのです。
2005年 nextmaruni 新たなスタート

「迷ったら原点に帰ろう。」
そこで取り組んだのが
国際的な外部デザイナーとの協業プロジェクト「nextmaruni」。
12人のデザイナーや建築家と協力し
「日本の思想や美意識から生まれた椅子」 を目指しました。
日本の美意識に対するメッセージを込めたこのプロジェクトが
新たな道を切り開いていったのです。
2008年 MARUNI COLLECTION発売

デザイナーを一人に絞り
深澤直人さんとの協働によってマルニ木工の技術を活かした
「MARUNI COLLECTION」の展開がスタート。
ここで、マルニ木工を代表する名作
「HIROSHIMA」が誕生しました。
100年使っても飽きのこないデザインと
堅牢さを兼ね備えた家具づくりを目指し
日本の木工技術とデザインの融合を追求。

2005年、2009年からは毎年、
世界最大級の国際家具見本市であるミラノサローネへ出展。
日本ではまだ珍しかったデザイナーズ家具は
やがて「世界のマルニ」として知られるまでに成長し
今もなお、国内外に影響を与え続けています。
また、マルニ木工を題材に
ノンフィクション作家・小松成美氏が取材、執筆した書籍
「奇跡の椅子 AppleがHIROSHIMAに出会った日」が
刊行されました!!✨

マルニ木工の挑戦と軌跡が描かれた一冊、
ぜひ皆さんもご一読ください♪
いかがでしたか?
マルニ木工の歴史を振り返ると
「すべての出来事に無駄なことはない」と強く感じます。
戦争やバブル崩壊といった
困難な時代を乗り越えてきたからこそ
培われた技術があります。
そして、その思いを受け継ぎながら
職人たちは今もなお進化を続けています。
妥協のない木材選び、卓越した職人技、
そして何より「ものづくりを楽しむ」姿勢。
ただ生産性を追い求めるのではなく
職人自身が楽しんで作ることを大切にしている。
「毎日が図工の時間だったら楽しくない?」
そんな言葉を担当の方が話してくれました。
それこそが、日本を代表する木工会社ならではの風景なのかもしれません。
ものづくりが好きだからこそ、木工の道を選んだ職人たち。
だからこそ、「迷ったら原点に帰る」ことで
新たな発想が生まれるのかもしれませんね😊
次回の記事では、工場見学通して学んだ
「製造工程」に焦点を当ててご紹介します!
お楽しみに〜♪
Shinc lab.スタッフが広島県のマルニ木工の工場を訪問しました。普段はなかなか見られない工場の様子を、ぜひ記事でご覧ください。